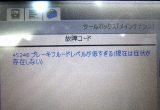ブレーキの点検
- 掲載日/2011年12月06日【R1100/1150GS基礎メンテ】
- このコンテンツは BMW BIKES Vol.51 掲載の記事を再編集したものです。
文・写真/ BMW BIKES 構成 / VIRGIN BMW.com
R1100/1150GS 基礎メンテ【ブレーキの点検】編

1100系フロントブレーキ
おなじみのブレンボ4ピストンキャリパー。

1150系フロントブレーキ
1150の後期からトキコ製キャリパーも採用されている。

ブレーキパッドの点検
パッドの残量の点検はしやすい。なお、ブレーキパッドは社外品が出回っているが、中にはGSの重量(+荷物)と、1150後期サーボブレーキに対して相性が悪いものが見受けられるので注意しておきたい。純正でもノーマルとサーボブレーキでは、パッド形状は同じでも素材を変えてあるのだ。

パッドの磨耗度
新品(下)との残量の比較。ブレーキパッドが磨耗すると、ヒートマス(熱容量)が低下し、過熱によるフェード現象やベーパーロックの原因となる。また、発熱により磨耗スピードも速くなる。1/3程度が交換時期と考えたい。

リアブレーキキャリパー
リヤは1100/1150系とも基本的に同じブレンボ片押し2ピストンキャリパー。これも、ノーマルとサーボブレーキではパッドの素材が異なる。

リアブレーキパッドの点検
完全に使用限度を通りこして、裏の鉄板とブレーキディスクが接触寸前。GSに限らずBMWユーザーはリヤブレーキの使用頻度が高いようだ。フロントより先に減ることが多い。

パッドの使用限界の確認
パッド裏の鉄板には穴が開いており、磨耗限界に達するとディスクが見えるようになっている。

リアブレーキパッドの交換
新品パッドは角の面取りと表面の平面出し、鳴き止め対策を施す。ピストンを押し込む前にピストンと周辺を洗浄し、スライドピンのグリスアップとスライドの点検。また、必ずリザーブタンクのキャップを開け、レベル点検とダイヤフラムの手直しを行なわないと、ブレーキ引きずりの原因。

ディスクローターの点検
ディスクの放熱兼水切り穴にブレーキ粉が詰まっている。良いことはひとつも無いので、細い棒ヤスリで掃除する。なお、ブレーキディスクの磨耗限度は、1100/1150系いずれも前後ともに4.5mm。新品状態では5.0mmである。

ブレーキホースの点検
ブレーキホースは定期交換部品。これは漏れが発生しているが、重要保安部品なので、こうなる前に交換したい。

ブレーキホースの交換
どうせ交換するなら、ステンメッシュのホースもある。これは社外品で、交換を機会にすべて入れ替えてみた。キット販売されていないので、すべて作成した。

ブレーキホースの取り回し
GSはハンドル切れ角やサスストロークが大きいうえに取り回しが複雑なので、角度や長さには気を遣う。

マスターシリンダーの点検
1100系のフロントブレーキマスターシリンダー。

ゴム系パーツの点検
下からゴムブーツをめくって、漏れをチェックする。1100の前期型は腐食しやすい。

マスターシリンダーの交換
腐食してフルードが漏れ出したマスターシリンダー。ここまで腐ると交換するしかない。

ダイヤフラムの点検・その1
これは1150のマスターシリンダー。BMWに限らず、マスターシリンダーのキャップ裏にはガスケットを兼ねたゴムのダイヤフラムが付く。パッドの磨耗につれてフルードレベルが下がっても、ダイヤフラムが変形することで、リザーブタンク内が負圧にならない(正圧を保つ)しくみだ。ところが、ダイヤフラムの変形度合いにも限度があるので、リザーブタンク内の正圧を保ちにくくなる。定期的にキャップを開けて変形を直してやる。

ダイヤフラムの点検・その2
リヤ側のキャップも同様。なお、パッド磨耗によってレベルが下がるのは正常なので補充の必要はない。中途半端に補充すると、パッドを新品に交換した際にピストンが押し戻されるのでリザーブタンクからフルードがあふれ、面倒なことになる。よほどレベルが低くないかぎり、ブレーキフルードの補充は必要ない。
R1100/1150GS基礎メンテ メニュー
- 【前の記事へ】

ホイールの点検 - 【次の記事へ】

ABSユニットの点検
関連する記事
-
R1100/1150GS基礎メンテ
スタンドの点検
-
R1100/1150GS基礎メンテ
電装系の点検
-
R1100/1150GS基礎メンテ
バッテリーの点検
-
R1100/1150GS基礎メンテ
GT1を使ったブレーキ点検
-
R1100/1150GS基礎メンテ
ABSユニットの点検
-
R1100/1150GS基礎メンテ
ホイールの点検
-
R1100/1150GS基礎メンテ
フロントサスペンションの点検
-
R1100/1150GS基礎メンテ
クラッチの点検




 第17回「ABSユニットの点検」
第17回「ABSユニットの点検」 R1100/1150GS基礎メンテ 記事一覧へ
R1100/1150GS基礎メンテ 記事一覧へ